院政期後半の政治についてまとめます。登場するのは後白河上皇と後鳥羽上皇。ただ、その前に保元の乱と平治の乱という2つの大きな戦いが起こるので、この乱から話をしていきます。
院政期後半の主な出来事
〈1156〉保元の乱
〈1159〉平治の乱
・長講堂領設置
・西面の武士設置
保元・平治の乱
鳥羽が亡くなったあと、上皇vs天皇の実権争いが起こります。ちなみにですが、上皇は複数いることが全然普通にあります。孫が天皇でパパもじーちゃんも上皇みたいな状態があるのです。だから鳥羽が死んだ直後も上皇がいました。
そんなときでも、一番強い人というのが存在する。この場合はおそらくパパよりもじいちゃんの方が強かったんでしょう。上皇が1人だろうが複数いようが、一番強い上皇のことを治天の君(ちてんのきみ)と言います。
話を元に戻します。崇徳上皇(すとく)と後白河天皇の争いが起こりました。崇徳が兄貴で後白河が弟という関係です。これを保元の乱と言いました。1156年のこと。
保元の乱のきっかけ
この乱が起きた背景には、崇徳上皇のあまりにもかわいそうな生い立ちがありました。崇徳と後白河、そしてもう1人受験では全く必要ない近衛天皇は、全て鳥羽の息子です。ただ、3人の中で崇徳だけは鳥羽と血のつながりがありませんでした。
前回、白河上皇は女好きだった話をしました。孫の鳥羽もかわいかった白河じーちゃんは、自分が1番かわいがっていた若い女性を嫁さんとして孫にプレゼントします。女性のみなさん、くれぐれも僕を怒らないでください。白河がやったことです。
ただ、この女性はこのときすでに身ごもっていました。つまり白河は自分の子付きでプレゼントしていたのです。クズっぷりがすごい(笑)。もちろん生まれた子に対して、鳥羽はなんの愛着もありません。
なので天皇にしたあとすぐに譲位させて上皇にします。天皇のままならば天皇としての権利があるけれど、上皇にしてしまえば治天の君は鳥羽なので何もできません。
こうして崇徳は全く楽しくない人生を過ごすのです。そして鳥羽が亡くなってもう弟しかいなくなったときについにキレた。これが保元の乱の始まりです。
保元の乱の経過
崇徳が藤原氏を味方にしたら、後白河はその藤原氏とケンカ中の別の藤原氏を味方にするという感じが続き、結果的には【上皇・藤原氏A・平氏A・源氏A】vs【天皇・藤原氏B・平氏B・源氏B】というもう訳の分からない戦いになりました。
この時点でもう名前がごちゃごちゃになるのが分かるでしょう。だから問題によく出るんですね。それが分かってても出るとこんがらがってしまうところ。完璧に覚えましょう。
崇徳上皇側:藤原頼長・平忠正・源為義・源為朝
後白河天皇側:藤原忠通・平清盛・源義朝
この戦いは後白河天皇が勝ちました。そのまま上皇となって院政を開始するのですが、勝った方には藤原氏・平氏・源氏が混ざっていました(どっちが勝ってもこの結果だけど笑)。
平治の乱
だから今度はその間で戦いが起こります。1159年平治の乱です。天皇家の内紛だった保元の乱と違い、こちらは平清盛vs源義朝という他氏同士のの争いです。こちらもメンツを覚えましょう。
【藤原通憲・平清盛・平重盛】vs【藤原信頼・源義朝・源頼朝】 藤原氏は左が「みちのり」、右が「のぶより」と読みます。ここで平氏が勝ち、平氏政権が誕生するのです。
後白河上皇
院政の話に戻ります。後白河上皇の時期は平氏政権とその後源氏が復活して最終的には平氏を滅ぼす時期と完全に重なります。この話は次回で。もう1つ、鳥羽の八条女院領のように、ここでも上皇の荘園が増えました。長講堂領と言います。
後鳥羽上皇
時代はもう鎌倉時代に入ってるけど、院政の流れで後鳥羽上皇の話までします。この人は後に承久の乱というでかい事件を起こします。上皇が鎌倉幕府に戦争を仕掛けた事件です。
武士のカタマリである幕府に仕掛けるということは、上皇も相当の軍事力を持っていたということ。源平勢を仲間に引き込んだ保元の乱とは訳が違うのです。つまりこの時期に上皇の軍隊を作ったのです。これを西面の武士と言います。
主にボディーガードが仕事の北面の武士に対して、こちらの西面の武士はちょっとした軍隊でした。人数はあまり変わらず多くはないけれど、上皇自らが選んだ少数精鋭の部隊です。
院政のまとめ
以上のように、院政というのは具体的には4人の上皇を覚えてもらえればOKです。そしてこの4人はそれぞれボディーガードが荘園を新しく設置しました。順番に北面の武士→八条女院領→長講堂領→西面の武士です。
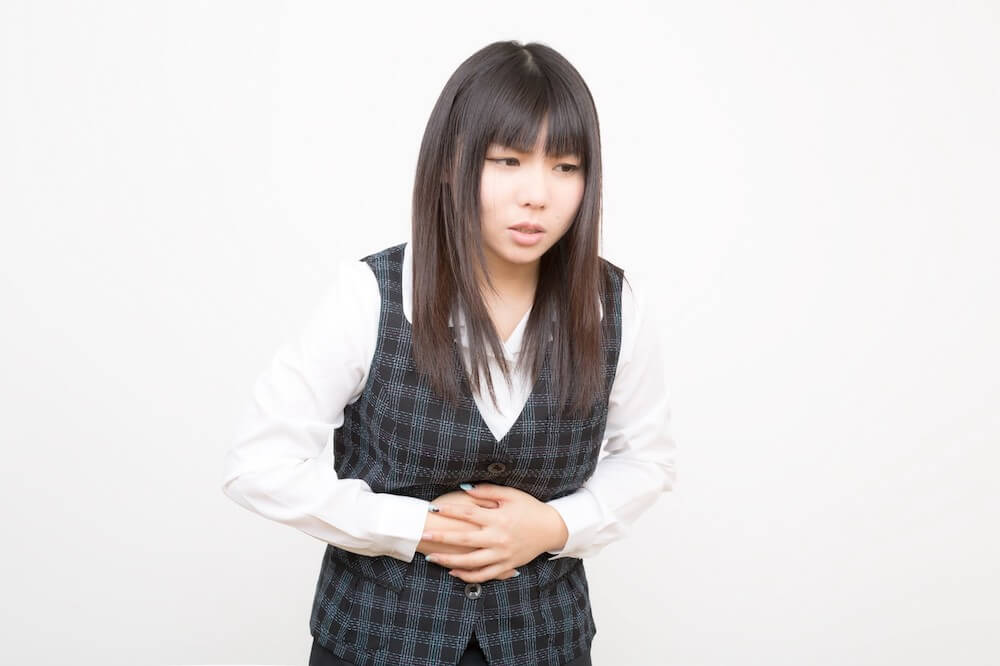






コメント